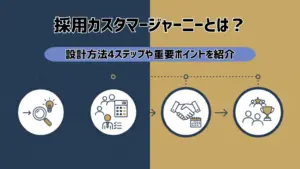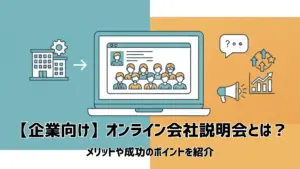合同説明会で呼び込みを成功させるコツとは?注意すべきNG行為も紹介

合同説明会は、多くの企業が一堂に会し、限られた時間の中で参加者に自社の魅力を伝える貴重な機会です。そこで重要になるのが「呼び込み」です。呼び込みが成功すれば、ブースに足を運んでもらえるだけでなく、その後の採用活動にも大きな影響を与えます。
そこで本記事では、合同説明会で効果的に呼び込みを行うコツと、避けるべきNG行為を紹介します。呼び込みの基本から成功のための具体的なポイントまで実践的な内容を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
合同説明会における「呼び込み」の重要性
合同説明会では、多くの企業が一堂に会し、限られた時間とスペースの中で参加者に自社の魅力を伝えなければなりません。単にブースを構えて待っているだけでは、多くの参加者に見過ごされてしまいます。そこで重要になるのが「呼び込み」です。
以下では、合同説明会における「呼び込み」の重要性について解説します。
参加者の行動パターンを考慮すると、待っているだけでは不十分
合同説明会に参加する求職者の多くは、最初に会場を歩き回り、どの企業の話を聞くかを決めます。この時点で目に留まらなければ、説明を聞いてもらう機会すら得られません。
参加者は限られた時間内で効率よく情報を得ようとするため、積極的な「呼び込み」がなければ、興味を持たれる前にスルーされてしまう可能性が高まります。
企業の第一印象を決定づける要素となる
合同説明会において、参加者が企業に対して抱く第一印象は「ブースの雰囲気」や「担当者の態度」に大きく左右されます。呼び込みが活発で明るい企業は、「活気がある」「話しやすそう」という印象を持たれやすく、参加者が自発的に足を運びやすくなります。
他社と競争する中で、参加者の関心を引く必要がある
合同説明会は、複数の企業が同時に求職者にアプローチする場であり、ある意味「競争の場」でもあります。同じ業界や職種の企業が複数並んでいる中で、何もしなければ埋もれてしまい、他社のブースに参加者を奪われてしまいます。
特に人気業界では、多くの企業が参加しているため、「呼び込み」によって目立つ努力をしなければ、興味を持ってもらうことすら難しくなります。
知名度の低い企業ほど、呼び込みの影響が大きい
大手企業や有名企業であれば、参加者は事前に情報を持っており、自発的にブースへ訪れることが期待できます。しかし、知名度の低い企業や中小企業の場合、呼び込みをしなければ参加者に気づいてもらえず、せっかく参加してもほとんど訪問者が来ないという事態に陥ることもあります。
合同説明会の限られた時間と機会を最大限に活かすためにも、呼び込みによって「まずは話を聞いてみよう」と思わせることが重要です。
合同説明会での成果が、採用の質と量に直結する
合同説明会でどれだけ多くの参加者に自社の話を聞いてもらえるかは、その後の採用活動に大きく影響します。呼び込みが成功し、多くの参加者と接点を持つことができれば、エントリーや選考に進む候補者の母数を増やせます。
合同説明会で呼び込みが成功しやすい企業ブースの特徴
合同説明会で呼び込みが成功しやすい企業ブースの特徴を、3つ紹介します。
ブースのデザインが目を引く
多くの企業が出展する合同説明会では、まず参加者の目に留まることが重要です。そのため、ブースのデザインが洗練されていたり、視覚的にインパクトがあったりする企業は、参加者からの注目を集めやすくなります。
具体的には、以下のような企業カラーを活かした統一感のある装飾品を効果的に使うことで、他社ブースとの差別化を図ることができます。
- テーブルクロス
- 椅子の背もたれ用カバー
- バナースタンド
- のぼり・スウィングバナー
- バックパネル
- フロアマット
- テント・横幕
総じてブースを「一目でどんな企業かがわかる」デザインで演出するのは効果的であり、業種や企業理念が視覚的に伝わるよう工夫されているブースは、参加者の足を止めやすくします。
パンフレットやノベルティが魅力的
パンフレットやノベルティも、呼び込み成功において大きな役割を果たします。単に配布するのではなく、「もらって嬉しい」「思わず手に取りたくなる」工夫が施されたアイテムは、参加者の関心を引くきっかけになります。
例えば、企業の特徴が一目でわかるデザインのパンフレットや、就活に役立つ情報を盛り込んだ冊子などは、「あとで読んでみよう」と思わせる力があります。
ノベルティについても、以下のように使用場面の多い文房具や直ぐに役立つエコバッグなど、実用性が高いものが人気です。
- エコバッグ・トートバッグ
- 文房具(ボールペン、シャープペン、ノート、メモ帳、付箋など)
- エコバッグ
- 自社製品の試供品
- タオル・ハンカチ
- ウェットティッシュ・ティッシュ類
- モバイルバッテリー・PCスマホグッズ
また、ブースでの説明を聞いた人限定で配布するなど、限定感を演出することも効果的です。
役割とバランスを考えてスタッフが配置されている
合同説明会では、ブースに立つスタッフの印象が、そのまま企業全体のイメージに直結します。そのため、ただ人を配置するのではなく、「親しみやすさ」と「専門性」のバランスを意識したスタッフ選びと配置が重要です。
参加者にとって話しやすい雰囲気を作るには、明るくフレンドリーな対応ができるスタッフの存在が欠かせません。一方で、仕事内容やキャリアパス、職場のリアルな様子など、具体的かつ深い質問にもしっかり答えられる専門性も求められます。
そのため、若手社員と人事担当者の両方を配置することで、「この企業で働くイメージが湧いた」「実際の働き方が聞けて参考になった」と参加者の満足度が高まりやすくなります。
親しみやすさだけでも、専門知識だけでも不十分です。学生の関心を引き、信頼を得るためには、両者のバランスが取れたスタッフ体制を整えてこそ、効果的な呼び込みにつながるのです。
合同説明会で呼び込みを成功させるコツ
合同説明会で呼び込みを成功させるための、具体的なコツを4つ紹介します。
印象の良い声かけ
呼び込みの第一歩は、参加者が足を止めたくなる「印象の良い声かけ」です。笑顔やアイコンタクトを意識し、フレンドリーな雰囲気で話しかけることも重要です。声のトーンを明るくし、押しつけがましくならない自然な呼び込みを意識しましょう。
また「こんにちは」「ぜひお話を聞いていきませんか?」といった一般的な呼びかけだけでは、他社と差別化できず、スルーされることが多くなります。
効果的な声かけのポイントは、参加者の興味や反応を引き出しやすいワードを盛り込むことです。例えば、以下のような声かけが有効です。
- 「〇〇業界に興味ありますか?」
- 「〇〇の仕事に少しでも興味があれば、ぜひお話しませんか?」
- 「どんな業界を見ていますか?」(質問形式で会話につなげる)
ターゲット層を見極める
合同説明会には、業界・職種に明確な興味を持っている参加者もいれば、「どの企業を見ればいいかわからない」と迷っている参加者もいます。やみくもに呼び込むのではなく、自社に合ったターゲット層を見極め、それに応じたアプローチを行うことが成功のカギです。
例えば、エンジニア職を募集している企業なら、「プログラミングに興味がある方はいますか?」といった具体的な声かけを行うことで、関心の高い参加者の足を止めやすくなります。
ターゲットに合った呼び込みができれば、ただブースに人を集めるだけでなく、その後の選考につながる質の高い接点を増やすことができます。
参加者と近い世代の社員に任せる
参加者が合同説明会で企業を選ぶ際、「実際に働くイメージが持てるかどうか」は大きなポイントになります。そのため、呼び込みを行うスタッフには、参加者と年齢の近い社員を配置すると効果的です。
例えば新卒採用の場合、若手社員であれば就活時の悩みや入社後のギャップなど、学生が知りたいリアルな情報を伝えやすいため、「この会社で働くのが楽しそう」「自分と合いそう」と感じてもらいやすくなります。学生目線でのアドバイスができるため、自然と会話が弾み、ブースへ誘導しやすくなるのもメリットです。
中途採用の場合は、実際に中途採用で入社した社員を起用すると、参加者の共感を得て呼び込みの成功率を高められるでしょう。
ただし、その後に業務内容や採用情報について詳しく説明できる人事担当者やベテラン社員も配置し、バランスの取れた体制を作ることが重要です。
説明会への誘導トークの工夫
呼び込みが成功しても、その場の立ち話だけで終わってしまっては意味がありません。参加者にブース内で話を聞いてもらうためには、説明会へ自然に誘導できるトークが重要です。
例えば、以下のようなトークが有効です。
- 「この業界の動向や働き方について、5分でわかる説明をしています!」(短時間で得られるメリットを伝える)
- 「〇〇の仕事に興味があるなら、詳しくお話しできるのでぜひ座ってみませんか?」(興味のあるテーマで引き込む)
- 「この後、〇時からスタートするので、少しだけ時間を取ってお話を聞いてみませんか?」(時間を具体的に伝え、参加のハードルを下げる)
- 「今ならノベルティも配布中です!ぜひお話を聞いて受け取ってください!」
参加者は複数のブースを回るため、できるだけ「聞いてみよう」と思わせる言葉を選び、参加への心理的ハードルを下げることが大切です。
合同説明会での呼び込みのNG行為
合同説明会では、多くの企業が限られた時間とスペースの中で参加者の関心を引こうとします。ただし、呼び込みの方法によっては、参加者に悪い印象を与え、逆効果になることもあります。ここでは、避けるべきNG行為を紹介します。
しつこく勧誘する
相手が一度断ったにもかかわらず、何度も声をかけたり、無理にブースへ誘導しようとするのは逆効果です。「ちょっと興味ないです」と言われた後に、「とりあえず話だけでも!」と食い下がると、企業の印象が悪くなりかねません。
合同説明会では、参加者は多くのブースを回るため、押しつけがましい対応は敬遠されがちです。むしろ、一度は興味を持たなかった参加者にも、後から「やっぱり話を聞いてみよう」と思ってもらえるような、柔軟かつ好印象な対応を心がけましょう。
自社ブースを大きく離れた場所で勧誘する
自社のブース周辺ではなく、通路の真ん中や他社のブース近くで声をかけるのは、マナー違反となる可能性があります。特に、参加者が他の企業の話を聞こうとしているタイミングで割り込むような呼び込みは、相手にも迷惑がかかります。
また、会場によっては、ブース外での過度な勧誘が禁止されていることもあるため、ルールを事前に確認することが大切です。参加者が自然に立ち寄りたくなるような呼び込みを、自社のブース内で工夫しましょう。
選考での優遇をほのめかす
「ブースに来てくれた方は、一次選考を免除します!」といった選考での優遇をほのめかす発言は、公平性を欠く印象を与えるだけでなく、企業の信頼性にも影響を与えかねません。
また、参加者が「ここに行けば簡単に内定がもらえるのでは?」と誤解し、本来の企業理解を深める機会が損なわれてしまう可能性もあります。採用活動はあくまで適性を見極める場であり、誤解を招くような表現は避けるべきです。
声が小さいなど自信がない印象を与える
呼び込みを行う際、声が小さく聞き取りづらかったり、ぼそぼそと話してしまったりすると、自信がない印象を与えてしまいます。参加者から見ても「この会社、大丈夫かな」と不安に思われてしまい、ブースに立ち寄る意欲を削いでしまう原因になります。
効果的な呼び込みには、適度な声量と明るいトーンが必要です。特に会場内は騒がしいことが多いため、意識してハキハキと話し、聞き取りやすい声を心がけましょう。
合同説明会の自社ブースに呼び込みやすくする工夫
多くの参加者が行き交う合同説明会では、ブースの存在に気づいてもらい、立ち寄ってもらうための仕掛けが欠かせません。
ここでは、呼び込みの成功率を高めるための具体的な工夫を、3つ紹介します。
体験型コンテンツの導入
ただ説明を受けるだけのブースよりも、実際の業務や社風を体感できる「体験型コンテンツ」を取り入れることで、通りすがりの人の興味を引きやすくなります。たとえば、簡単な業務のシミュレーションや製品のデモ体験、チームワークを感じられるミニワークショップなどは効果的です。
体験を通じて「この会社で働くイメージが湧いた」と感じてもらえれば、説明会後の応募や面談への意欲にもつながります。
SNSやQRコードを活用した情報提供
会場では時間に限りがあるため、すべての情報を伝えるのは難しいものです。そこで、QRコードを使ってSNSや採用サイトへスムーズに誘導し、補足的な情報提供ができる仕組みを整えると便利です。
特にSNSは、イベント当日の様子や社員のリアルな声、社内の雰囲気を視覚的に伝えられるため、参加者との距離を縮めるきっかけになります。QRコードはパンフレットやブースのパネル、配布ノベルティなどにも組み込みましょう。
現役社員への質疑応答の実施
リアルな声が聞ける「現役社員との会話」は、参加者の不安を取り除き、信頼感を生み出す大きな要素です。説明担当者だけでなく、実際に現場で働く社員をブースに配置し、自由に質疑応答ができる時間帯を設けることで、「気軽に話せる雰囲気」を演出できます。
このとき、業務内容だけでなく、働き方や入社後のギャップ、ライフスタイルとの両立といった、リアルな疑問にも答えてもらえるようにすると、より関心を持ってもらいやすくなります。
合同説明会での呼び込みを強化するための準備
合同説明会で多くの参加者をブースに呼び込むためには、当日の声かけだけでなく、事前準備が重要です。準備の精度を高めることで、より効果的に関心を引きつけ、説明会後のアクションにつながります。
ここでは、呼び込みを成功させるための具体的な準備について紹介します。
事前に呼び込みのシナリオを作成しておく
合同説明会の会場では、限られた時間の中で多くの企業が参加者へアピールを行います。そのため、場当たり的な声かけではなく、ターゲットに合わせた「呼び込みのシナリオ」を事前に作成しておくことが重要です。
例えば、次のようなシナリオを用意しておくと、スムーズに対応できます。
- 初対面の参加者向け
「こんにちは!〇〇業界に興味はありますか?私たちは△△に強みを持つ会社です。よろしければ少しお話を聞いてみませんか?」 - 業界に関心がありそうな参加者向け(手持ちのパンフレットなどで確認)
「〇〇業界を検討中の方ですか?当社は△△の特徴を持ち、未経験の方でも活躍できる環境を整えています。詳しくお話ししましょう!」 - すでに他社の説明を受けた参加者向け
「いくつかブースを回られましたか?他社と比較しやすいように、当社の特徴を簡単にご説明しますね!」
このように、場面ごとに異なる声かけを用意することで、より効果的な呼び込みが可能になります。
説明会当日の役割分担を決ておく
合同説明会では、参加者への呼び込み、ブース内での説明、質疑応答、資料配布など、さまざまな対応が求められます。すべてを同じ人が対応するのではなく、役割を明確に分担することでスムーズに進行できます。
■役割の例
- 呼び込み担当
ブース周辺で参加者へ声をかけ、興味を持ってもらう役割。明るく、親しみやすい対応ができる人が適任。ターゲット層に近い世代・立場だとなお良い。 - プレゼン担当
ブース内で企業説明を行う役割。事業内容や募集要項をしっかり説明できるように準備しておく。 - 質疑応答・フォロー担当
参加者の個別の質問に対応する役割。現場の実情を伝えられる現役社員が望ましい。 - 資料・ノベルティ配布担当
パンフレットやノベルティを渡しながら、参加者にブースの情報を提供する役割。
これらの役割を事前に決め、各自の担当範囲を明確にしておけば、当日もスムーズな運営を実現できるでしょう。
他社との差別化ポイントを明確にしておく
合同説明会では多くの企業が参加し、同じ業界・職種での競争が激しくなります。そのため、事前に「他社と何が違うのか」を明確にし、参加者に伝わりやすい形で整理しておくことが重要です。
■差別化ポイントの例
- 企業文化の違い
「当社は社内の風通しが良く、経営陣との距離が近いのが特徴です」 - キャリアパスの独自性
「未経験からでも〇年で△△のポジションを目指せる研修制度があります」 - 福利厚生や働き方の強み
「フレックスタイムやリモートワークを導入し、柔軟な働き方が可能です」
事前にこれらのポイントを整理し、ブース内での説明にも落とし込んでおくことで、参加者に強く印象を残せます。
まとめ
合同説明会での呼び込みは、企業の第一印象を左右し、採用活動の成果に直結します。成功する呼び込みには、印象の良い声かけ、ターゲット層を見極めたアプローチ、そしてブースの魅力的なデザインとノベルティの活用が重要です。
加えて、スタッフの配置にも工夫を凝らし、参加者との信頼関係を築くことが成功へのカギとなります。ただし、しつこい勧誘や不適切な場所での呼び込みは逆効果を生むため、注意が必要です。
これらのコツを活かし、合同説明会で自社の魅力を最大限に伝えることで、採用活動における成功をつかみましょう。
なお弊社はダイレクトリクルーティング支援企業として、過去60万件・全40媒体以上のソーシングデータを用いて、自社が求める人材の採用を最短ルートで成功に導くサポートを行っています。
最短かつ高いコストパフォーマンスで求める人材を獲得したいとお考えの方は、ぜひ以下の「問い合わせフォーム:無料」から気軽にお問い合わせください。

45分の気軽な相談会を
開催しています

竹村 朋晃
著者プロフィール 竹村 朋晃(Tomoaki Takemura)
株式会社ダイレクトソーシング 代表取締役CEO
▶︎ LinkedInプロフィールを見る
2005年に野村総合研究所に入社。大手損害保険会社のシステム設計・開発に従事し、エンジニアとしてのキャリアをスタート。 2015年、ダイレクトソーシングの可能性に着目し、株式会社ダイレクトソーシングを創業。データドリブンな採用を軸に、候補者データの構造化、スカウト改善、タレントプール構築などを通じて、累計500社以上の採用支援を行う。 2017年よりLinkedIn公式パートナーとして、日本企業へのLinkedIn活用を支援。2025年には「LinkedIn Student Career Week」を主催し、5,000名超の学生と40社超の企業をマッチングさせるなど、イベントプロデュースでも実績多数。 「Stand Alone Complex Society(個が独立し共創する社会)」の実現を掲げ、採用における価値創造を追求している。 趣味はウェイクボードとテニス。お台場在住。技術と営業を横断する“ハイブリッド人材”として、採用の進化に挑み続けている。
関連記事