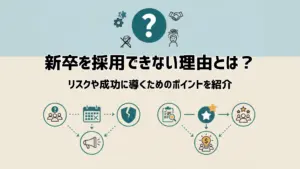【企業側】合同説明会のメリットとは?デメリットと注意点も紹介

合同説明会は、多くの企業が参加し、求職者と直接コミュニケーションを取る貴重な場です。
短時間で多数の求職者にアプローチできることや、コスト削減につながる点など、企業側にとって大きなメリットがあります。
ただ一方で、競争の激しさや限られた時間の中での情報伝達の難しさといったデメリットも無視できません。
そこで本記事では、合同説明会の基本的な仕組みを説明した上で、企業側が得られるメリット・デメリットを詳しく解説します。
また、合同説明会を成功させるためのポイントについても紹介するので、採用活動の一環として活用を検討している企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
合同説明会とは

合同説明会とは、複数の企業が一堂に会し、求職者に向けて自社の魅力をアピールするイベントです。
求職者には、新卒の学生や中途の転職希望者が含まれます。具体的には、就職情報サイトが企画する大規模イベントや大学主催のキャリアフェアなどが挙げられます。
「短時間で多くの求職者にアプローチを行える」「単独説明会よりも参加者を集める負担が少ない」といったメリットがある一方で、「限られた時間とスペースのため深い説明は難しい」「競争が激しく埋もれるリスク」などのデメリットもあります。
メリットとデメリットの詳細は、以降の項目で詳しく紹介します。
なお昨今はオンライン形式でも行われています。各企業は会場内のブースの代わりに時間交代で自社の説明を行うのが一般的です。
オンラインのため、全国の求職者にリーチでき、移動コストが不要ですが、雰囲気や熱量が伝わりにくい点は課題です。
単独説明会(個別説明会)との違い
単独説明会(個別説明会)とは、1つの企業が自社だけで説明会を開催するイベントです。
]つまり、単独説明会と合同説明会では、参加企業数と開催規模が異なります。
単独説明会の場合、
「自社の魅力をじっくり伝えられる」
「企業と学生の距離が近い」
「会社の雰囲気を直接的に伝えられる」
などはメリットです。ただし
「自社のみによる集客や会場準備など準備の負担が大きい」
「参加者は既に自社に関心をもっている求職者に偏る」
などのデメリットもあります。
なお単独説明会もオンラインでの開催が増えてきており、メリットやデメリットは合同説明会と同様です。
合同説明会の企業側におけるメリット

合同説明会の企業側におけるメリットを、5つ紹介します。
コスト削減につながる
合同説明会では、多くの企業が同じ会場に集まり、一度に多数の求職者に向けて説明を行います。
そのため、単独の会社説明会を開催する場合に比べて、会場費や運営費、広報費などのコストを抑えることが可能です。
つまり、複数の企業と共同でイベントが運営されるため、集客のための広告宣伝費を削減できる点が大きなメリットといえます。
さらに、合同説明会に参加することで、遠方の大学へ個別訪問する必要が減り、移動費や人件費の節約にもつながります。
短期間で多くの求職者と接点を持てる
合同説明会は、1日や数日間の開催期間内に数百人から数千人規模の求職者が参加するため、多くの学生と効率的に接触できます。
ブースを訪れた求職者と直接会話し、短時間で自社の魅力を伝えられるため、採用活動の初期段階において母集団を形成するのに適しています。
また、限られたリソースの中で効率よく多くの求職者に接触できるため、採用担当者の負担を軽減する効果もあります。
自社の認知度向上につながる
合同説明会には、多くの学生が集まるため、自社をまだ知らない求職者に対してもアプローチする機会が得られます。
特に知名度の低い企業や中小企業にとっては、求職者の視野に入る貴重な場となります。
さらに、説明会で配布するパンフレットやノベルティ、ブースのデザインなどを工夫することで、参加者の印象に残りやすくなり、企業名の認知度を向上させることが可能です。
他社との比較を通じた自社の魅力の明確化
合同説明会では、多くの企業が同じ会場で求職者と交流するため、各参加者は複数の企業を比較しながら情報を収集します。
この環境を活用することで、他社との差別化ポイントを強調し、自社の独自の魅力を伝えやすくなります。
また、学生からの質問や反応を通じて、他社に対する自社の強みや改善点を見つけることもできるため、採用戦略のブラッシュアップにもつながります。
多様な求職者層にアプローチできる
合同説明会には、新卒であれば様々な大学・学部・学科、中途であれば様々な業界・職種など多様なバックグラウンドを持つ求職者が参加します。
そのため、特定の大学や学部に依存せず、幅広い学生層にアプローチできる点が大きなメリットです。
特に文理や職種の枠を超えた採用を考えている企業にとっては、多様な求職者と接点を持つ良い機会となります。
さらに、地方の求職者や留学や海外転勤などグローバルな経験をもった人材など、通常の採用活動では接触しにくい層とも出会える可能性があります。
また、あえて業界や職種に特化して開催される合同説明会もあるため、ターゲット層を絞って採用活動を行いたい場合に有効です。
合同説明会の企業側におけるデメリット

合同説明会の企業側におけるデメリットを3つ紹介します。
限られた時間とスペースのため深い説明は難しい
合同説明会では、多くの企業が同じ会場で説明を行うため、1社あたりに割り当てられる時間やスペースが限られています。
特に、人気企業のブースは回転率が高く、1人ひとりの参加者とじっくりと説明する時間を確保するのが難しくなります。
そのため、自社の事業内容や強み、企業文化を深く理解してもらう前に求職者が次の企業へ移動してしまうケースも少なくありません。
オンラインの場合も、交代制で時間割で区切られているケースが多く、いずれにしても限られた時間のなかで印象に残る情報を伝える工夫が欠かせません。
競争が激しく埋もれるリスク
合同説明会には、大手企業から中小企業まで幅広い企業が参加するため、参加者の注目を集めるための競争が激しくなります。
特に知名度の低い企業や業界全体の認知度が低い場合、学生に気づかれず埋もれてしまうリスクが高まります。
また、人気企業のブースには多くの参加者が集まりやすい一方で、集客に苦戦する企業もあります。
そのため、ブースのレイアウトや説明方法、呼び込み方などを工夫し、学生の関心を引く施策を講じることが重要です。
自社に合わない求職者も多く訪れる可能性
合同説明会では、多種多様な求職者が参加するため、自社の採用ターゲットとは異なる参加者がブースを訪れることもあります。
例えば、特定のスキルや資格を必要とする職種の場合、興味を持った求職者がいても実際の選考には進めない可能性が高くなります。
また、広く認知を獲得できるメリットがある一方で、エントリーの母集団が広がりすぎることで、選考の工数が増え、採用プロセスの効率が下がる可能性もあります。
事前にターゲット層を明確にし、適切なアプローチを考えることが重要です。
合同説明会を成功させるポイント

合同説明会を成功させるために重要なポイントは、以下の4つです。
ブースの装飾や配置を工夫する
合同説明会では、多くの企業が一堂に会するため、自社のブースが目に留まるような工夫が求められます。
具体的には、企業のブランドカラーを活かした装飾や、大きく見やすいロゴ・キャッチフレーズの掲示など、遠くからでも認識しやすいデザインを取り入れると効果的です。
また、開放的なレイアウトにすることで、参加者が気軽に立ち寄りやすい雰囲気を作ることも大切です。
配布物やパンフレットの配置にも工夫を凝らし、手に取りやすい場所に設置することで、より多くの情報を届けられるでしょう。
呼び込みや司会進行は対象者と近い世代の社員に任せる
求職者と年齢が近い社員が呼び込みや進行を担当することで、参加者に親近感を与え、自然なコミュニケーションが生まれやすくなります。
例えば、数年前に入社した若手社員が担当することで、企業の雰囲気や働くイメージをよりリアルに伝えることが可能です。
また、実際の経験談を交えた会話ができるため、求職者が具体的な働き方を想像しやすくなり、企業への興味を引き出す効果も期待できます。
短時間で伝わるようにプレゼンの質を高める
合同説明会では、一人ひとりに割ける時間が限られているため、短時間で効果的に魅力を伝えられるよう、プレゼン内容を工夫する必要があります。
具体的には、特に伝えたいポイントや結論を明確にし、インパクトのあるスライドやビジュアルを活用することで、求職者の関心を引きやすくなります。
なお説明に用いるスライドについては「1スライド:1メッセージ」を心がけましょう。
また、業界特化の説明会でもない限りは専門用語を多用せず、シンプルかつ具体的な言葉で伝えると、理解度を高められます。
さらに、短時間でも印象に残るエピソードやストーリーを交えると、より強い印象を与えられます。
開催前にリハーサルを行い、社内関係者からのフィードバックを得ておくのもおすすめです。
特に「想定よりも時間がかかる・時間が足りない」となりがちなので、リハーサルを通じてより端的かつ短時間にポイントを分かりやすく伝えられるようにすれば、プレゼンの質はより高まるでしょう。
参加者へのフォローを徹底する
合同説明会は求職者との最初の接点となることが多いため、イベント後のフォローが重要です。
例えば、説明会で名刺や連絡先を交換した参加者には、後日メールやメッセージを送ることで関心を維持しやすくなります。
自社の採用情報や選考フローを改めて案内することで、応募につながる確率も高まります。
また、単独説明会や個別相談会、会社訪問の機会を提供することで、さらに詳しく企業を知ってもらうきっかけを作ることができます。
合同説明会を活用すべき企業とは?

「自社も合同説明会に参加すべきなのか」を迷っている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、合同説明会を活用すべき企業の特徴を紹介します。以下が当てはまる場合は、活用を推奨します。
知名度が低い企業
知名度が低い企業にとって、合同説明会は自社を多くの求職者に認知してもらう絶好の機会です。
特に、大手企業のブランド力に埋もれがちな中小企業や新興企業は、個別の採用活動ではアプローチできる層が限られてしまうことが多くあります。
合同説明会に参加することで、多くの求職者の目に触れる機会を増やし、企業の強みや独自の魅力を直接伝えられるため、ブランド認知度の向上につながります。
もちろん、どうしても知名度が高い企業のブースに人は集まりがちですが、「ついでに見てみようかな」からの訪問も期待できるため、単独説明会でゼロから集客をするよりも接点を得られる可能性は高いといえます。
そこで求職者と直接対話し、社風や働く環境の魅力を具体的にアピールできれば、企業の印象を強く残すことができます。
採用コストを抑えたい企業
採用活動には、多くのコストがかかります。求人広告の掲載費、採用イベントの運営費、個別説明会の開催費など、費用がかさむ中で、合同説明会は比較的低コストで多くの求職者にリーチできる手段の一つです。
特に、単独説明会を開催する余裕がない企業にとって、合同説明会は一度に多くの求職者と接点を持てるため、採用効率の向上が期待できます。
また、採用にかかる時間や人的リソースを削減できる点も魅力です。合同説明会で興味を持った求職者に対して、選考フローをスムーズに進めることで、採用活動全体のコストパフォーマンスを高めることができます。
幅広い層にリーチしたい企業
特定の層だけでなく、多様な人材を採用したい企業にとっても、合同説明会は有効な手段です。通常の合同説明会には、業界や職種にこだわらず、さまざまなバックグラウンドを持つ求職者が参加します。
そのため、企業側としては、特定のターゲット層だけでなく、想定していなかった新しい層との出会いが生まれる可能性があります。
例えば、専門職を希望する人だけでなく、異業種からの転職希望者や、幅広い職種に興味を持つ人材とも接点を持てるため、多様な採用の選択肢が広がります。
こうした幅広いリーチによって、企業の成長を支える新たな人材を確保するチャンスが増えるのです。
なお、特定の業界・職種の人材と接点をもちたい場合には、特化型の合同説明会への出展を検討すると良いでしょう。
まとめ
合同説明会は、コストを抑えながら多くの求職者と接点をもち、企業の認知度を向上させるなど多くのメリットを有する有効な手段です。
ただし、時間の制約や競争の激しさといったデメリットもあるため、事前の準備が重要になります。
ブースのデザインや呼び込み方法を工夫し、短時間でも効果的に魅力を伝えられるプレゼンを用意することで、求職者の印象に残る説明会を実現できます。
また、ターゲット層を明確にし、自社に合った人材と出会えるような戦略を立てることが成功の鍵です。
合同説明会を上手く活用し、効果的な採用活動につなげていきましょう。
また、弊社はダイレクトリクルーティング支援企業として、過去60万件・全40媒体以上のソーシングデータを用いて、自社が求める人材の採用を最短ルートで成功に導くサポートを行っています。
最短かつ高いコストパフォーマンスで求める人材を獲得したいとお考えの方は、ぜひ以下の「問い合わせフォーム:無料」から気軽にお問い合わせください。


45分の気軽な相談会を
開催しています

竹村 朋晃
著者プロフィール 竹村 朋晃(Tomoaki Takemura)
株式会社ダイレクトソーシング 代表取締役CEO
▶︎ LinkedInプロフィールを見る
2005年に野村総合研究所に入社。大手損害保険会社のシステム設計・開発に従事し、エンジニアとしてのキャリアをスタート。 2015年、ダイレクトソーシングの可能性に着目し、株式会社ダイレクトソーシングを創業。データドリブンな採用を軸に、候補者データの構造化、スカウト改善、タレントプール構築などを通じて、累計500社以上の採用支援を行う。 2017年よりLinkedIn公式パートナーとして、日本企業へのLinkedIn活用を支援。2025年には「LinkedIn Student Career Week」を主催し、5,000名超の学生と40社超の企業をマッチングさせるなど、イベントプロデュースでも実績多数。 「Stand Alone Complex Society(個が独立し共創する社会)」の実現を掲げ、採用における価値創造を追求している。 趣味はウェイクボードとテニス。お台場在住。技術と営業を横断する“ハイブリッド人材”として、採用の進化に挑み続けている。
関連記事