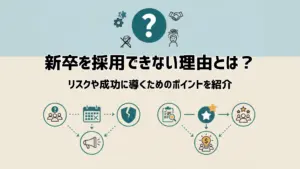採用直結型インターンとは?メリットや注意点、実施条件を紹介

採用直結型インターンとは、インターンシップを通じて優秀な学生を発掘し、採用活動に直接つなげることを目的としたプログラムです。
政府により新たなインターンシップの定義が示され、採用直結型インターンが公式に認められたことから、実施する企業が増加傾向にあります。
そこで本記事では、採用直結型インターンについて、定義やメリット、注意点、実施要件、成功させるための重要ポイントを紹介します。
目次
採用直結型インターンとは

採用直結型インターンとは、インターンシップを通じて優秀な学生を発掘し、採用活動に直接つなげることを目的としたプログラムです。
従来の職場体験型インターンとは異なり、企業と学生のマッチングを重視し、早期の関係構築や内定、採用に結びつけることを目指します。
以前は、学業への影響を懸念して採用に直結したインターンシップの実施を認めていませんでした。
しかし、2022年に政府が「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」を一部改正したことで、採用直結型インターンが可能となりました。
つまり、採用直結型インターンでは、実施に際して学生から得た情報を採用活動に用いることが可能となります。
例えば、インターンシップを採用の応募条件としたり、インターンシップの結果を基に次の採用プロセスへ進めるかを判断したりといったことが公式に認められたのです。
採用直結型インターンを行うメリット

採用直結型インターンを行うメリットを、3つ紹介します。
早い時期に優秀な学生との接点をもてる
優秀な学生と早期に出会える点は、採用直結型インターンのメリットです。
インターンは通常の採用活動よりも前倒しで行うことが多く、他社が本格的な採用活動を開始する前に、自社の魅力を学生に伝える機会を得られます。
特に就職活動を積極的に行う学生やスキルの高い学生は、インターンへの参加意欲が高い傾向にあります。
企業としては、こうした学生と早期に接触機会が増えることで、採用競争を有利に進められるのです。
マッチ度の高い採用につながりやすい
採用直結型インターンでは、企業と学生が互いに深く理解し合う機会が多くあります。
インターン期間中に学生が実際に業務に携わることで、企業は学生のスキルや仕事への姿勢を具体的に把握できます。
一方、学生も職場の雰囲気や企業文化を実際に体験することで、入社後のイメージを持ちやすくなります。
このように双方向の理解を深める仕組みがあるため、企業と学生のミスマッチを予防でき、定着率の向上にもつながるでしょう。
その結果として、採用後の育成コストや離職リスクを軽減可能です。
採用ブランディングにつながる
採用直結型インターンを成功させることは、自社の採用ブランディングに直結します。参加した学生からポジティブな口コミを生むだけでなく、SNSや就職関連サイトを通じて広まり、学生にとって魅力的な企業として認知されるきっかけとなるのです。
また、採用直結型インターンを導入している企業は、「自社と学生とのマッチ度を重視した企業」といった印象を持たれやすく、採用競合との差別化を図るポイントとなります。
こうした採用活動における透明性や魅力が、今後の採用活動全般にも良い影響を与えるでしょう。
採用ブランディングについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
採用ブランディングのポイント | 株式会社ダイレクトソーシング
採用直結型インターンの注意点

採用直結型インターンを行う上での注意点は、以下の3つです。
政府による定義を理解して実施要件を満たす
採用直結型インターンを実施する際は、まずインターンシップの定義を正確に理解しておくことが欠かせません。
2023年、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の三省合意によって、インターンシップの定義が見直されました。
これにより、従来「インターンシップ」と称されていた様々な取り組みは、以下の4タイプに再定義されています。
- タイプ1:オープン・カンパニー
企業理解や業界理解を主な目的としたプログラム。学生が企業の業務内容や職場環境、特定の業界について理解するための説明会や短期プログラムが該当します。 - タイプ2:キャリア教育
学生のキャリア観や就業意識を高めるための教育プログラム。就活アドバイスセミナーや産学協働プログラムなどが挙げられます。 - タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ
汎用的能力活用型は5日間以上、専門活用型は2週間以上で実施するプログラム。実施期間の半分以上は、実際の就業体験が必要。従来のインターンシップのイメージに最も近いといえます。 - タイプ4:高度専門型インターンシップ
修士や博士課程を主な対象として、長期(2か月以上)で実施するプログラム。ただし、政府の定義においても「試行中」とされています。
つまり、インターンシップと定義されるのは「タイプ3」と「タイプ4」のみであり、同様に採用直結型インターンが認められるのもこの2タイプのみです。
条件の詳細については、後の項目で解説します。
社内リソースを確保できるか確認しておく
採用直結型インターンを成功させるには、十分な社内リソースの確保が不可欠です。
インターン生を受け入れるには、指導担当者の配置や業務内容の準備、進捗管理など、多くのリソースが必要になります。
特に採用直結型インターンは、企業と学生が長期的に関わるため、現場の負担が大きくなる可能性があります。
そのため、受け入れ部署の調整や社員教育の時間確保など、事前に社内体制を整えておくことが重要です。
また、企業としてインターン生をサポートする体制が不十分だと、学生にマイナスの印象を与えてしまうリスクがあるため、計画段階でのリソース確認が欠かせません。
採用直結型インターンを実施するための要件

採用直結型インターンを実施するための要件を、5つ紹介します。
いずれも政府による新定義において示された実施条件です。
罰則や法的な拘束力はありませんが、公的な方針を遵守している方が採用ブランディングにはプラスに作用します。
実施期間は少なくとも5日間以上
採用直結型インターンを実施する場合、少なくとも5日間以上のプログラムを組む必要があります。
厳密には、前述した政府による新定義の「タイプ3」は、「汎用的能力インターン」と「専門活用型インターン」の2つに分かれており、それぞれの必要実施期間は下記の通りです。
- 汎用的能力インターン
分野を問わずあらゆる学生が参加可能なインターン
必要実施期間:5日間以上 - タイプ2:専門活用型インターン
特定の分野における専門性を有した学生向けのインターン
必要実施期間:2週間以上
短期間のプログラムでは、学生が企業の業務や職場環境を十分に理解する時間が足りず、インターンの効果が限定的になる可能性があるためです。
一方、5日間以上の期間を設ければ、学生は企業の仕事内容や文化に深く触れることができるだけでなく、企業側も学生の適性やポテンシャルをより正確に見極められるメリットがあります。
特に採用直結型インターンは、相互理解を深めることを目的としているため、一定期間の実施が成功の鍵となります。
なお本要件により、以前は一般的であった「1dayインターンシップ」のような名称での開催は認められず、新定義に準拠するためにはタイプ1の「オープン・カンパニー」などに名称を変更しなければなりません。
実施期間の半分以上を就業体験に充てる
採用直結型インターンでは、実施期間の半分以上を就業体験に充てることが条件のひとつとされています。
座学や説明会だけでは、学生が企業の実態を理解するのは困難なためこうした要件が設けられています。
実際の業務を経験させることで、学生は自分が企業で働くイメージを具体的に描けるようになります。
就業体験は実際の職場で行う
就業体験を実施する際は、実際の職場で行うことが必須条件です。
つまり、会議室などでの業務シミュレーションやロールプレイングなどでは、政府が示す要件から外れてしまうことになります。
学生にオフィスや現場の雰囲気を直接感じてもらうことで、働く環境についてよりリアルな理解を深めることができます。
また、現場で実務に触れることで学生は企業の価値観や仕事の進め方を肌で感じ取れるため、魅力が直接的に伝わり志望度を高める機会となるでしょう。
企業としては、実際の職場での就業体験を通じて、学生の実務能力やコミュニケーションスキルを把握し、採用後のミスマッチを防ぐ効果を期待できます。
就現場社員が指導とフィードバックを行う
採用直結型インターンでは、現場社員が学生に対して指導やフィードバックを行う体制の整備が求められます。
学生にとって、現場のプロフェッショナルから直接指導を受けられるのは貴重な経験であり、業務理解を深める大きな助けになります。
また、フィードバックを通じて学生が自身の強みや改善点を理解できれば、成長意欲を高める効果も期待できます。
一方で、企業側も学生の適性や課題を明確に把握することができ、採用判断の質を高められます。
そのため、現場社員の協力を得る仕組みづくりが重要といえるのです。
長期休暇期間に実施する
採用直結型インターンは、夏休みや春休みといった長期休暇期間に実施することも要件として定められています。
長期休暇期間であれば、学生は学校の授業や課題に縛られることなく、フルタイムでインターンに参加できるため、より深い業務体験が可能となります。
業界によっては繁忙期と重なるケースもありますが、学生の立場でのスケジューリングを設定することで応募数および参加数が変化するため、留意しておきましょう。
採用直結型インターンを成功させる重要ポイント

採用直結型インターンを成功させるために重要なポイントを4つ紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
社内の理解と協力を得ておく
採用直結型インターンを成功させるには、社内全体の理解と協力が欠かせません。現場での就業体験が必須のため、特に配属先に所属する各現場社員の協力は不可欠です。
例えば、実務を支援する社員の確保や、指導・フィードバックを行う役割を明確にする必要があります。
また、企業全体で「採用直結型インターンが自社の採用活動にどのような効果をもたらすのか」を事前に共有し、インターン期間中の部署間の連携や、インターン生との適切な接し方などを想定しておくことが大切です。
社内の協力体制を構築することで、インターンの質を高め、参加学生にとって有意義な経験を提供でき、結果として自社への志望度向上を期待できます。
広報と集客に注力する
優秀な学生にインターンへ参加してもらうためには、効果的な広報と集客戦略が欠かせません。
自社のホームページや採用サイトでの情報発信はもちろん、就職情報サイトやSNS、大学のキャリアセンターなどを活用して、積極的にインターン情報を公開しましょう。
特に「採用直結型」であることを明確にし、学生にとっての魅力やメリットを具体的に伝えることが効果的です。
例えば、「特別な選考プロセスへ進める」「実践的な業務体験ができる」といった学生目線のメリットを打ち出せば、応募者の関心を引くことができます。
採用競合との差別化を図る
採用直結型インターンの成功には、他社との差別化を図ることが重要です。
多くの企業がインターンシップを実施していますが、自社ならではの強みや魅力を打ち出せば、優秀な学生を引きつけられます。
例えば、業界の最前線で働く社員との交流機会を設けたり、実際のプロジェクトに参加できるプログラムを用意するなどが有効です。
また、適正な報酬や交通費の支給、学びを得やすい環境の整備を通じて、学生の満足度を高めることも重要な差別化要素です。
採用競合にはない独自性を明確にし、学生に「この企業で働きたい」と思わせるインターンシップを実現しましょう。
実施後からの選考プロセスをスムーズにつなぐ
採用直結型インターンの効果を最大限に引き出すためには、インターン終了後の選考プロセスをスムーズに進めることも重要です。
インターンシップで企業の魅力を感じた学生が、その後の選考で離脱してしまわないように、早い段階で内定につながるフローを設計しましょう。
具体的には、インターン終了時に評価やフィードバックを行い、面接や選考に進む流れを案内すると効果的です。
また、選考日程の柔軟な調整や、迅速な連絡対応を心がけることで、学生にとっても負担が少なく、企業に対する好印象が高まります。インターンから採用までの一貫した流れを意識することが、成功の鍵となります。
まとめ
採用直結型インターンとは、インターンシップを通じて優秀な学生を発掘し、採用活動に直接つなげることを目的としたプログラムです。
インターン実施に際して学生から得た情報を採用活動に用いて、次の選考プロセスへつなげます。2022年に政府がインターンシップに関する定義や方針を一部改正したことで、公式に認められるようになりました。
採用直結型インターンは「早い時期に優秀な学生と接点をもてる」「マッチ度の高い採用につながる」「採用ブランディングにつながる」といったメリットがありますが、「政府による実施要件の遵守」「社内リソースの十分な確保」などには注意が必要です。
特に実施要件については、本部内で紹介していますので、参考にしてください。
また、採用直結型インターンを成功させるためには、「社内の理解と協力の確保」「広報と集客への注力」「採用競合との差別化」などが重要なポイントとなります。
各ポイントをおさえることで、自社が求める人材の採用につながるインターンを実現しましょう。
なお弊社はダイレクトリクルーティング支援企業として、過去60万件・全40媒体以上のソーシングデータを用いて、自社が求める人材の採用を最短ルートで成功に導くサポートを行っています。
最短かつ高いコストパフォーマンスで求める人材を獲得したいとお考えの方は、ぜひ以下の「問い合わせフォーム:無料」から気軽にお問い合わせください。


45分の気軽な相談会を
開催しています

竹村 朋晃
著者プロフィール 竹村 朋晃(Tomoaki Takemura)
株式会社ダイレクトソーシング 代表取締役CEO
▶︎ LinkedInプロフィールを見る
2005年に野村総合研究所に入社。大手損害保険会社のシステム設計・開発に従事し、エンジニアとしてのキャリアをスタート。 2015年、ダイレクトソーシングの可能性に着目し、株式会社ダイレクトソーシングを創業。データドリブンな採用を軸に、候補者データの構造化、スカウト改善、タレントプール構築などを通じて、累計500社以上の採用支援を行う。 2017年よりLinkedIn公式パートナーとして、日本企業へのLinkedIn活用を支援。2025年には「LinkedIn Student Career Week」を主催し、5,000名超の学生と40社超の企業をマッチングさせるなど、イベントプロデュースでも実績多数。 「Stand Alone Complex Society(個が独立し共創する社会)」の実現を掲げ、採用における価値創造を追求している。 趣味はウェイクボードとテニス。お台場在住。技術と営業を横断する“ハイブリッド人材”として、採用の進化に挑み続けている。
関連記事