新卒を採用できない理由とは?リスクや成功に導くためのポイントを紹介
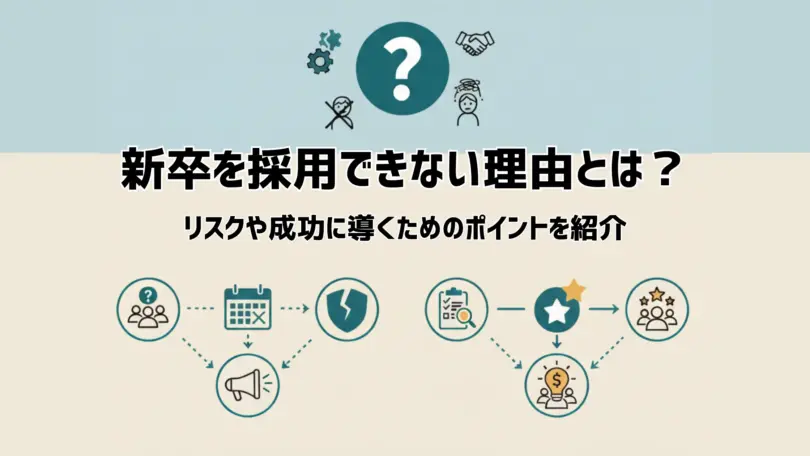
「新卒を採用できない」と悩む企業は少なくありません。少子化による競争激化や採用手法のミスマッチなど、新卒を採用できない理由はさまざまです。
そこで本記事では、新卒採用が難しくなる主な理由と、それによって企業が抱えるリスクについて解説します。あわせて採用成功のためのポイントも紹介しますので、課題の把握と改善にお役立てください。
新卒を採用できない理由
新卒を採用できない主な理由を、8つ紹介します。
少子化で採用競争が激化している
日本において少子化が進行するなか、そもそも新卒の求職者の母数が減少しています。その結果、市場全体として目標とする人数を採用しにくい状況にあるのです。
特に地方では、大学進学を機に都市部へ流出する若者が多く、地元企業が採用活動を行っても対象となる学生自体が少ない状況にあります。
また、別途解説するように大手企業やブランド力のある企業が先行して優秀な学生を確保するため、中小企業や知名度の低い企業は、志望先の候補に乗ることすら難しくなっているのも現実です。このように、絶対的な新卒人口の減少が採用難の大きな要因となっています。
新卒採用の開始時期が遅い
新卒採用市場では、スケジュールの前倒しが進んでおり、早い企業は大学3年次の夏頃からインターンシップを通じて学生と接触しています。採用活動のスタートが遅れると、既に他社への志望度が固まってしまい、応募者を確保することが難しくなります。
また、新卒採用は年度ごとの採用計画が影響するため、計画自体が遅れると、十分な母集団形成をできず、結果として「採用できない」状況に陥りやすくなるのです。
採用手法が自社に合っていない
新卒採用の手法は多様化しており、求人サイトへの掲載や合同説明会の参加だけでは、十分な応募が集まらないケースが増えています。
例えば、知名度や採用に充てられる人員や予算が不足しているにも関わらず、大規模な採用イベントへの出展から大手求人サイトのみを用いた母集団形成で苦戦してしまうケースは起こりがちです。その他、オンライン採用が一般化するなかで、従来の対面中心の採用活動にこだわると、求職者との接点を持ちにくくなるでしょう。
このように自社の業種・規模・求める人材・予算に適した採用手法を選択できていないことが、新卒採用が成功しない原因の一つとなっています。
知名度が不足している
知名度が低い企業は、新卒求職者の応募先として選ばれにくいのが実状です。学生は企業名を知っているかどうかでエントリーするかを判断する傾向が強いため、知名度の高い企業に応募が集中し、そうでない企業には目を向けてもらえないことが多くなります。
また、知名度が低いと、就職活動の情報収集の段階で学生の選択肢に入らず、エントリーの候補にすら入れない状況に陥るケースも少なくありません。
自社の魅力を上手くアピールできていない
企業の魅力が適切に伝わらないと、新卒求職者の関心を引くのは困難です。
例えば、給与や福利厚生といった表面的な条件だけをアピールしても、学生は長期的なキャリアの観点から就職先を選ぶため、働く環境や成長機会、社風などの要素が伝わらなければ、選考への進捗率が低下します。
また、採用ページや説明会の内容が抽象的で具体性に欠ける場合、学生にとって「どんな会社なのか」が分かりにくく、応募をためらう要因になります。
新卒が求める条件を満たしていない
近年の新卒求職者は、給与や福利厚生だけでなく、ワークライフバランス、成長環境、キャリアパスの明確化など、さまざまな条件を重視しています。
例えば、「テレワーク可」「副業OK」などの柔軟な働き方を求める学生も増えており、これらのニーズに対応できない企業は選択肢から外されやすくなるでしょう。
また、教育研修制度やキャリア支援が不十分な企業は、成長意欲の高い学生から敬遠される傾向があります。
募集時と選考時の印象にギャップが生じている
求人情報や説明会で伝えた企業のイメージと、実際の選考過程や職場の雰囲気にギャップがあると、学生は不安を感じ、選考を辞退するケースが増えます。
例えば、「社内の風通しが良く、若手が活躍できる」とアピールしていたのに、面接官が一方的な評価をするだけの選考だと、「本当に風通しが良いのか?」と疑問を持たれかねません。
また、会社説明会やオープンカンパニーなどでは、採用担当者や先輩社員の対応および印象が良かったのにも関わらず、選考時において面接官の対応が不親切だったり、選考スピードが遅かったりすると企業への印象が悪くなり、結果的に採用が難しくなります。
内定フォローが不足している
内定を出した後に適切なフォローを行わなければ、学生は他社と比較しながら意思決定を進めるため、内定辞退が発生しやすくなります。
特に、就職活動が長期化する傾向にあるなかにおいて、内定後のフォローを怠ると、「本当にこの会社で良いのか?」という迷いが生じ、より魅力的なオファーやフォローを行う企業へ流れてしまいかねません。
また、内定後に適切な情報提供や交流機会を設けないと、企業理解が深まらず、入社意欲が低下してしまうケースもあるでしょう。
新卒を採用できない企業が抱えるリスク
新卒を採用できない企業が抱える主なリスクは、3つ挙げられます。
高齢化による人材不足の深刻化
新卒採用ができない状況が続くと、社内の年齢構成が偏り、高齢化が進行します。特に、中小企業や地方の企業では、もともと若手人材が少ない傾向にあるため、新卒採用の停滞は将来的な人材不足を加速させてしまうのです。
また、現場のノウハウを次世代に引き継ぐ機会が減ることで、技術や知識の継承が難しくなり、事業の継続性に影響を及ぼす可能性があります。特に、専門的な技術や経験が必要な業界では、ベテラン社員の引退に伴う技術の断絶が深刻な問題となり得るでしょう。
企業文化の硬直化
新卒採用が滞ると、新しい価値観や発想を持つ若手社員が組織に加わらず、企業文化が固定化しやすくなります。長年勤めている社員だけで組織が構成されると、これまでのやり方が当たり前になり、変化に対応する柔軟性が失われるリスクが高まるのです。
また、新卒採用によって形成される「同期」という関係が生まれないため、社内の横のつながりが希薄になり、コミュニケーションの不活性化も引き起こしかねません。結果として、組織の閉鎖性が強まり、新しいアイデアが生まれにくい環境ができてしまう可能性もあります。
さらに、新卒社員が持つ「成長意欲」や「挑戦する姿勢」が企業全体に好影響を与えることも多いですが、その機会が失われることで、現場のモチベーション低下や組織の活力減退にもつながるでしょう。
新規事業やDX推進の遅れ
企業が成長を続けるためには、新規事業の立ち上げやデジタル技術の活用(DX推進)が不可欠です。しかし、新卒採用ができず、若手人材が不足すると、これらの取り組みが停滞するリスクが高まります。
新規事業の立ち上げには、新しい発想や市場への柔軟な適応力が求められますが、既存の社員だけではこれまでの成功体験に囚われ、新しいアイデアを生み出しにくくなります。特に、デジタルネイティブ世代が持つ感覚やITスキルは、DX推進の鍵となるため、若手の不在はデジタル化の遅れにも直結します。
また、DX推進には、新しいツールやシステムの導入だけでなく、それを使いこなす人材の育成も重要です。ただ、既存の社員がデジタル技術に不慣れな場合、導入したシステムを十分に活用できず、業務効率化や生産性向上が進まないケースも起こりがちです。新卒採用を通じてデジタル人材を確保しないと、競争力の低下につながる可能性があるでしょう。
新卒を採用できない状態から成功に導くためのポイント
新卒を採用できない状態から成功に導くためのポイントを、6つ紹介します。
採用マーケティングを行う
採用マーケティングとは、求める人材を獲得するために、自社や他社を含めた採用市場、
採用ターゲット層などを分析して、より効率的な採用活動を実現することです。
新卒採用市場では、企業が待っているだけでは応募が集まりにくくなっています。そのため、自社の魅力を戦略的に発信し、ターゲットとなる学生に適切なアプローチを行う採用マーケティングの重要性が増しています。
具体的には、採用サイトやSNSを活用して企業の情報を発信するほか、ターゲットとなる学生が興味を持つようなコンテンツ(社員インタビュー、職場の雰囲気を伝える動画など)を提供することが有効です。
また、自社に適した求人サイトやダイレクトリクルーティングサービスを利用して、積極的に自社の情報を届けることも欠かせません。
採用マーケティングを適切に行うことで、企業の認知度向上だけでなく、企業文化や仕事の魅力を理解したうえで応募する学生が増え、ミスマッチの低減にもつながります。
採用マーケティングについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
採用マーケティングとは?メリットや手順、用いる手法・サービスを紹介 | 株式会社ダイレクトソーシング
新卒採用の開始時期を見直す
近年の新卒採用市場では、採用スケジュールが早期化傾向にあります。そのため、自社の採用活動の開始時期が競合他社よりも遅れると、優秀な学生の獲得が難しくなる可能性があります。
特に、人気のある企業や大手企業は、大学3年生の夏頃からオープンカンパニーやインターンシップを通じて早期接触を始めています。そのため、採用活動の開始時期を早め、ターゲットとなる学生と早期に接点を持つことが重要です。
具体的に「新卒採用はいつからいつまでか」を理解した上で、優位に新卒採用を進めたい場合は、こちらの記事をあわせてご活用ください。
【人事向け】新卒採用はいつから?いつまで?検討と判断の重要ポイントを紹介 | 株式会社ダイレクトソーシング
採用ブランディングに取り組む
採用ブランディングとは、企業理念やビジョン、職場の雰囲気、そこで働く魅力・メリットなどを外部に発信し、採用市場における自社のブランド化を図ることです。
新卒採用を成功させるためには、企業の認知度だけでなく、「どのような企業であるか」というブランドイメージを確立するのが重要です。特に、中小企業や知名度が低い企業では、学生に対して「働きたい」と思わせる魅力を発信する必要があります。
採用ブランディングの具体的な方法としては、以下のような施策が挙げられます。
- 自社の強みや理念を明確に打ち出す
- 社員インタビューや職場紹介を通じて、リアルな社風を伝える
- 採用サイトやSNSで、企業の魅力を継続的に発信する
また、直近の内定者や若手社員にヒアリングを実施し、学生目線で共感を得やすいコンテンツを作成することも有効です。採用ブランディングが成功すれば、学生からの応募意欲が高まり、エントリー数や内定承諾率の向上につながります。
採用ブランディングのポイントについては、こちらの記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
採用ブランディングのポイント | 株式会社ダイレクトソーシング
ダイレクトリクルーティング(スカウト採用)を取り入れる
従来の新卒採用では、求人サイトに求人情報を掲載し、学生からの応募を待つ「待ちの採用」が主流でした。しかし、近年では企業側から求める人材へ積極的かつ直接的にアプローチを行える「ダイレクトリクルーティング(スカウト採用)」が注目されています。
ダイレクトリクルーティングを活用すれば、企業が求める人材に対して直接オファーを送れるため、マッチ度の高い学生との接点を得やすくなります。特に、企業を認知していなかった学生にも接触できるため、新たな採用機会を生み出せるメリットは大きいでしょう。
スカウト型のサービスを活用し、データベース上で自社に合った人材を見極めながらアプローチを行うことで、採用成功率を高められます。
ダイレクトリクルーティング(スカウト採用)について、こちらの記事で詳しく紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。
スカウト型採用とは?メリット・デメリットと手順、重要ポイントを紹介
待遇やキャリアパスの明確化
新卒採用において、学生は「この会社で成長できそうか」「長く働き続けられる環境はあるか」といった点を重視します。そのため、給与や福利厚生だけでなく、キャリアパスや教育体制を明確に示すのが重要です。
特に、中小企業では「入社後の成長をイメージできない」といった理由で学生に敬遠されるケースが多いため、以下のような情報を積極的に発信するとよいでしょう。
- キャリアパスの例を具体的に提示する
例:〇年後に〇〇職へ昇進可能など - 教育制度の内容を詳しく紹介する
例:新入社員研修やOJT、eラーニング支援など - 社員の成長事例を伝える
例:実際に活躍している若手社員のインタビューなど
学生が将来のキャリアを明確にイメージできるようにすることで、企業への安心感が高まり、エントリー意欲の向上につながります。
オープンカンパニーやインターンシップを実施する
新卒採用を成功させるためには、学生に自社の魅力を直接伝え、理解を深めてもらう機会を設けることが重要です。その手段として、オープンカンパニーやインターンシップの実施が効果的です。
オープンカンパニーでは、企業の概要や仕事内容を紹介し、学生に興味を持ってもらうことを目的とします。具体的には、企業の説明会、先輩社員との座談会・交流会、職場見学などが挙げられます。
一方で、インターンシップは、実際の業務を体験してもらい、企業文化や働く環境をリアルに感じてもらう機会です。インターンシップを通じて、学生の自社や実務に対する理解が深まり、選考への意欲が高まるだけでなく、企業側も学生の適性を見極めやすくなります。特に長期インターンシップを活用すると、実際の業務を通じて優秀な学生との関係値を築きやすくなります。
まとめ
新卒を採用できない理由には、少子化による採用競争の激化、採用開始時期の遅れ、知名度不足、採用手法のミスマッチなどが挙げられます。
こうした状況が続くと、人材不足の深刻化や企業文化の硬直化、新規事業やDX推進の遅れといったリスクが生じるため、適切な対策が求められます。
そして採用の成功には、早期からの学生との接点づくり、自社の魅力発信、ターゲットに合った採用手法の選定が不可欠です。今一度、自社の採用戦略を見直し、持続的な成長につなげていきましょう。
また今回は、新卒を採用する手段としても有効なダイレクトリクルーティング(スカウト採用)を行える具体的なサービスを1つのPDF資料にまとめた「ダイレクト採用メディアおすすめ53選」を無料でプレゼントします。
「手っ取り早く各種ダイレクト採用メディアのまとまった情報が欲しい」
という方向けに最新の比較資料(2025年7月時点)を作成しました。
本記事以上に、多くの媒体と詳細な情報を掲載しています。
選定ポイント/中途採用向けメディア一覧/新卒採用向けメディア一覧 等


45分の気軽な相談会を
開催しています

竹村 朋晃
著者プロフィール 竹村 朋晃(Tomoaki Takemura)
株式会社ダイレクトソーシング 代表取締役CEO
▶︎ LinkedInプロフィールを見る
2005年に野村総合研究所に入社。大手損害保険会社のシステム設計・開発に従事し、エンジニアとしてのキャリアをスタート。 2015年、ダイレクトソーシングの可能性に着目し、株式会社ダイレクトソーシングを創業。データドリブンな採用を軸に、候補者データの構造化、スカウト改善、タレントプール構築などを通じて、累計500社以上の採用支援を行う。 2017年よりLinkedIn公式パートナーとして、日本企業へのLinkedIn活用を支援。2025年には「LinkedIn Student Career Week」を主催し、5,000名超の学生と40社超の企業をマッチングさせるなど、イベントプロデュースでも実績多数。 「Stand Alone Complex Society(個が独立し共創する社会)」の実現を掲げ、採用における価値創造を追求している。 趣味はウェイクボードとテニス。お台場在住。技術と営業を横断する“ハイブリッド人材”として、採用の進化に挑み続けている。
関連記事








