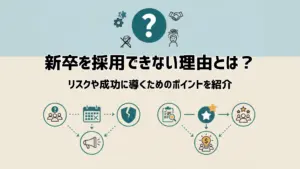新卒採用人数の決め方|規模別の目安や注意点を紹介

「新卒採用を行うが、適切な採用人数が分からない」「同規模の他社は、何人くらい採用しているのだろうか」など、新卒採用人数についての悩みや迷いを抱えている企業は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、採用人数について、従業員規模別の目安を示した上で、決め方と注意点を紹介します。あわせて、新卒採用での人数確保が向いている企業の特徴と、中途採用が向いている企業の特徴も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
新卒採用人数の目安|規模別
新卒採用人数の目安を従業員規模別で紹介します。
以下の表は、採用予定人数を計1,261社に確認したものです。従業員規模ごとに4つに分類し、それぞれの平均値を算出しています。ただし、各企業ごとで経営状況や人員計画は異なるため、あくまで目安としましょう。
■採用予定数(2025年卒)
| 従業員規模 | 採用予定人数 | 回答企業数 |
|---|---|---|
| 300人未満 | 6.9人 | 407社 |
| 300~999人 | 18.9人 | 438社 |
| 1,000~4,999人 | 50.0人 | 324社 |
| 5,000人以上 | 141.8人 | 87社 |
新卒採用での人数確保が向いている企業の特徴

新卒採用での人数確保が向いている企業の特徴を、3つ紹介します。
理念や企業文化の継承を重視する
理念や企業文化は、企業が成長し続けるための重要な基盤です。これを次世代に継承するには、新しい人材を計画的に迎え入れることが不可欠です。
新卒採用では、社会人経験のない若者を採用して理念や価値観をゼロから教育するため、自社の「色」に染めやすいといえます。成長後には、自社の理念と価値観を体現した社員となることを期待できるでしょう。
特に長い歴史をもつ企業や自社の価値観を重視する企業にとっては、理念の共有が従業員の団結力を高め、長期的な成長につながるため、新卒採用での人数確保は有効な手段となるのです。
「組織の若返り」を図りたい
5年後や10年後など将来的な組織内の年齢構成を想定した際、高齢層に偏りが見られる場合には、新卒採用で「組織の若返り」を図る必要があります。
また、組織の平均年齢が高くなると、固定化した考え方や働き方が根付いてしまいがちです。これを打破し、活気ある職場を取り戻すにも、新卒採用による若手人材の積極的な確保が有効です。とりわけ急速に変化する市場や技術革新の波に対応する必要がある企業にとって、若返りは重要な課題となります。
若手社員の活躍は、職場全体に新しいエネルギーをもたらし、組織の活性化にもつながります。そして将来的なリーダー候補として計画的に育成することで、企業の競争力向上につながるでしょう。
若手社員の発想や創造性を求めている
変化の激しいビジネス環境において、新しい発想や柔軟な思考が求められる場面は増えています。新卒社員は、固定概念にとらわれない柔軟なアイデアや、新しい視点を企業にもたらしてくれます。
特に、イノベーションが求められる業界や、既存のビジネスモデルを変革する必要がある企業にとって、新卒採用は重要な戦略の一つです。
また、若手社員の視点を活かすことで、顧客ニーズの変化に迅速に対応できる商品やサービスの企画・開発を期待できます。エンドユーザーが若い企業には、特に当てはまります。若手の創造性を取り入れることで、企業全体の競争力を大きく向上できるでしょう。
新卒より中途採用での人数確保が向いている企業の特徴

新卒よりも、中途採用での人数確保が向いている企業の特徴を、3つ紹介します。以下の特徴に当てはまる場合は、新卒採用よりも中途採用での人数確保を検討すべきでしょう。
早期に人員を補充する必要がある
新規プロジェクトの立ち上げや事業拡大に伴う人材不足、担当社員の急な離職などに直面する企業では、即戦力となる人材を早急に確保しなければなりません。
中途採用は、既に職務経験がある人材を採用できるため、即戦力としての活躍を期待できます。一方、新卒採用では教育期間や現場に慣れるまでの時間が必要になるため、即効性には限界があります。
そのため、特に短期間で成果を出すことが求められる環境・状況では、中途採用の人数確保が効率的かつ適しているといえるのです。
業務に専門性や特定のスキルを求められる
高度な専門知識や特定のスキルを必要とする業務を担う人材を求めている場合、中途採用が適しています。例えば、データ分析の専門家や法務担当者など、即座に専門性の高い実務をこなせるスキルを備えた人材は、新卒採用では困難です。
中途採用であれば、該当分野の実績や資格を持つ経験者を採用できるため、研修やスキル習得にかかる時間を短縮できます。また、過去の業務経験を基に、新たな視点や知見を企業に提供してくれる点も中途採用の大きな利点です。
育成面など新人を受け入れる体制が整備されていない
新卒社員を受け入れるには、OJTや研修プログラム、メンター制度などの育成体制が必要です。一方でこうした体制が十分に整っていない企業では、教育に時間とリソースを割く余裕がなく、新卒採用が難しい場合があります。
中途採用は既に基本的なビジネスマナーや業務スキルを持つ人材が多いため、新卒採用と比べると育成時の負担は少なく済むでしょう。特に、少人数の企業や成長途上でリソースが限られている企業では、中途採用が現実的な選択肢といえます。
新卒採用人数の決め方
新卒採用人数の決め方を4ステップで解説します。
1. 企業としてのビジョンや目標を明確にする
新卒採用人数を決める際には、自社の企業としてのビジョンや目標を明確にすることが前提となります。中長期的にどのような組織となり、何を達成するのかを明確化することで、必要な人材像および採用人数の方向性が見えてくるのです。
また、成長戦略や事業拡大の具体的な目標を設定することで、採用活動の基盤を固められます。例えば、売上の大幅な増加や新規事業への進出を目指す場合、それに必要な若手人材の数を逆算することで、より現実的な採用人数を算出できます。この段階で目標と採用の結びつきをしっかりと意識することが、採用活動全体を成功に導くポイントです。
2. 中長期的な事業計画に基づいた人員計画を立てる
次に、企業の中長期的な事業計画をもとに、人員計画を立てます。例えば、3年後に新規プロジェクトを立ち上げる予定がある場合、そのプロジェクトを推進するための人材の人数を具体的に見積もる必要があります。
また、既存事業の成長に伴い、どの部署でどれだけの人員増が必要かを部門ごとに洗い出すことも重要です。同時に、退職や異動による自然減を見込み、新卒社員の役割をどの程度補完させるかを検討します。
こうした計画に基づいて採用人数を決定することで、経営戦略に沿った人材の確保が可能となるのです。
3. 予算から採用可能な人数を割り出す
新卒採用人数を確定する際には、採用予算との兼ね合いを慎重に検討する必要があります。採用活動には、求人広告費や採用イベント参加費、面接や選考プロセスにかかる人件費など、多くのコストが発生します。
さらに、採用後の研修費用や初年度の給与、福利厚生なども考慮しなければなりません。これらの費用を合算し、予算内で採用可能な人数を算出することで、無理のない採用計画を立てましょう。
4. 各部門や部署との調整を経て人数を確定させる
採用人数を最終的に確定するためには、各部門や部署との綿密な調整が欠かせません。それぞれの部門が抱える人材ニーズを具体的に把握し、協議の上で採用人数を確定します。
また、全体のバランスを考慮しながら、採用人数を適切に配分することも重要です。部門ごとの意見を取り入れつつも、全社最適を重視した視点で調整を行うことで、現場と経営陣の双方が納得する新卒採用計画が完成します。
新卒採用人数を決める際の注意点
新卒採用人数を決める際の注意点を、4つ紹介します。
現実的な採用人数を設定する
新卒採用人数を決める際には、企業の実状に沿った現実的な採用人数を設定する必要があります。過大な採用目標を掲げてしまうと、予算などのリソースが不足したり、もし達成できても教育体制への負担が増大したりして、組織全体の運営に悪影響を及ぼす可能性があるためです。
反対に必要最低限の人数しか採用しない場合、急な退職や想定外の人員不足に対応できなくなるリスクもあります。そのため、経営目標や人員計画を考慮した上で、事業規模と予算に見合った現実的な人数設定が求められます。
選考辞退・内定辞退の想定と予防を行う
新卒採用では、選考プロセスの途中で辞退する学生や、内定後に辞退する学生が一定数いることを想定して人数を決めなけれなりません。学生優位の売り手市場が続く昨今では、特に慎重に検討すべきといえます。
参考までに、「採用予定人数を100」とした場合の「内定出し人数」「内定辞退人数」「内定人数」を規模別で示した表を紹介します。
■「採用予定人数を100」とした場合の内定関連人数
| 従業員規模 | 内定出し人数 | 内定辞退人数 | 内定人数 | 回答企業数 |
|---|---|---|---|---|
| 300人未満 | 130.4 | 64.1 | 66.1 | 197 |
| 300~999人 | 161.9 | 86.9 | 74.4 | 264 |
| 1,000~4,999人 | 123.8 | 60.9 | 61.5 | 177 |
| 5,000人以上 | 170.1 | 82.5 | 80.7 | 50 |
この表から、内定を出した人数のうち、内定を辞退した人数と内定を受け入れた人数は、およそ半数ずつであることが分かります。ただし例外的に「300〜999人」は、内定辞退人数86.9に対して内定数74.4と、辞退者の方が多くなっています。いずれにしても、内定者のうち約半数は辞退に至る傾向を読み取れます。
また、辞退を防ぐためには、選考プロセスの段階で自社の魅力を伝えるのはもちろん、内定後にも継続的なフォローを行うことが欠かせません。これにより、採用人数を確保しつつ、優秀な人材の入社率を高めましょう。
人数によって適した採用手法は異なる
採用人数に応じて、最適な採用手法を選択することも重要なポイントです。
例えば、大人数の採用が必要な場合は、大規模な合同説明会や大手求人サイトなど、多くの学生にアプローチできる手法が適しています。ウェブ広告を大々的に打ち出して、企業の認知度を高める施策も有効です。
一方、少人数の採用を目指す場合は、大学ごとの説明会やリファラル採用といったターゲットを絞った方法が効果的です。とりわけ、自社が欲しい人材を選んで直接アプローチ可能なダイレクトリクルーティング(スカウト採用)は、特に注目されています。
教育体制や現場の受け入れ体制を整えておく
採用人数を決める際には、入社後の教育体制や現場での受け入れ体制が十分に整備されているかを確認しましょう。
例えば、大人数を採用する場合には、研修プログラムの拡充や指導担当者の配置が必要です。少人数採用でも、既存社員が新入社員をフォローする時間やリソースが確保されていなければ、教育が十分に行き届かず、早期離職のリスクが高まります。
現場の負担を考慮しつつ、新入社員がスムーズに成長できる環境を整えることも、新卒採用を成功させるために欠かせないポイントです。
まとめ
新卒採用人数は従業員規模別で異なり、従業員数が300人未満で6.9人、300〜999人で18.9人、1,000~4,999人で50.0人、5,000人以上で141.8人でした(2025年卒の調査結果を参考)。
特に理念や企業文化の継承を重視する場合や「組織の若返り」を図りたい場合、若手社員の発想や創造性を求めている場合などには、新卒採用での人数確保が向いています。
対して、早期の人員補充が必要な場合や業務に専門性や特定のスキルを求められる場合、育成面など受け入れ体制が未整備の場合などには、中途採用の方が向いている可能性が高いでしょう。
続いて、新卒採用人数の決め方を「企業のビジョンや目標の明確化」から「各部門・部署との最終調整」まで4ステップで紹介しました。「選考辞退・内定辞退の想定と予防」「人数によって異なる適切な採用手法」など注意点とあわせて、参考にしてください。
また少人数を採用する際、特に有効な手段として、優秀な人材に直接アプローチ可能なダイレクトリクルーティング(スカウト採用)を紹介しました。募集を待つだけでは成果を期待しにくい昨今において、特に注目される採用手法です。
弊社はダイレクトリクルーティング支援企業として、過去60万件・全40媒体以上のソーシングデータを用いて、自社が求める人材の採用を最短ルートで成功に導くサポートを行っています。
最短かつ高いコストパフォーマンスで求める人材を獲得したいとお考えの方は、ぜひ以下の「問い合わせフォーム:無料」から気軽にお問い合わせください。

45分の気軽な相談会を
開催しています

竹村 朋晃
著者プロフィール 竹村 朋晃(Tomoaki Takemura)
株式会社ダイレクトソーシング 代表取締役CEO
▶︎ LinkedInプロフィールを見る
2005年に野村総合研究所に入社。大手損害保険会社のシステム設計・開発に従事し、エンジニアとしてのキャリアをスタート。 2015年、ダイレクトソーシングの可能性に着目し、株式会社ダイレクトソーシングを創業。データドリブンな採用を軸に、候補者データの構造化、スカウト改善、タレントプール構築などを通じて、累計500社以上の採用支援を行う。 2017年よりLinkedIn公式パートナーとして、日本企業へのLinkedIn活用を支援。2025年には「LinkedIn Student Career Week」を主催し、5,000名超の学生と40社超の企業をマッチングさせるなど、イベントプロデュースでも実績多数。 「Stand Alone Complex Society(個が独立し共創する社会)」の実現を掲げ、採用における価値創造を追求している。 趣味はウェイクボードとテニス。お台場在住。技術と営業を横断する“ハイブリッド人材”として、採用の進化に挑み続けている。
関連記事