【企業向け】カジュアル面談でよくある逆質問|具体例と回答例を紹介
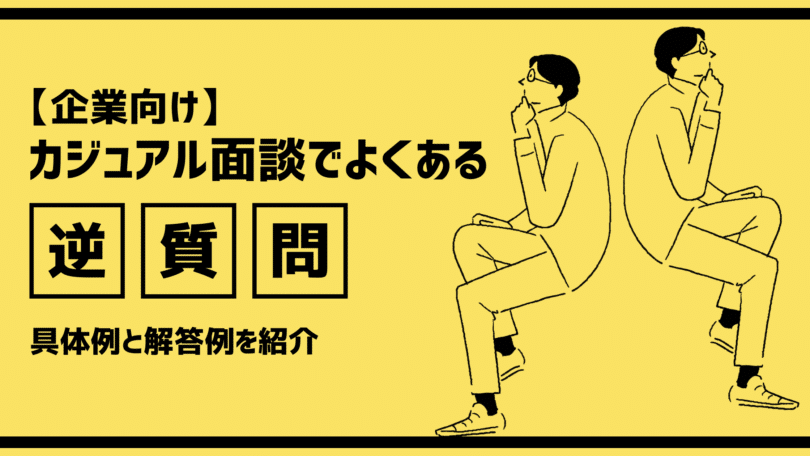
カジュアル面談で候補者から投げかけられる「逆質問」。
たかが雑談の延長、と受け流していませんか?
実はこの“逆質問タイム”こそ、候補者が企業のカルチャーや現場温度感を見極める瞬間であり、企業にとっては志望度を高めるための重要なタッチポイントです。
面談側がうまく対応できていないと、せっかくの関心が冷めてしまうことも…。
この記事では、カジュアル面談における逆質問の役割や準備方法、実際によくある質問例などをもとに、採用成功率を高めるためのヒントをまとめました。
チーム内での面談トレーニングにも役立てていただける内容です。
✅ この記事でわかること
面接の属人化・評価のバラつきといった悩みを解消するための、実践的なトレーニングプログラムをご紹介しています。
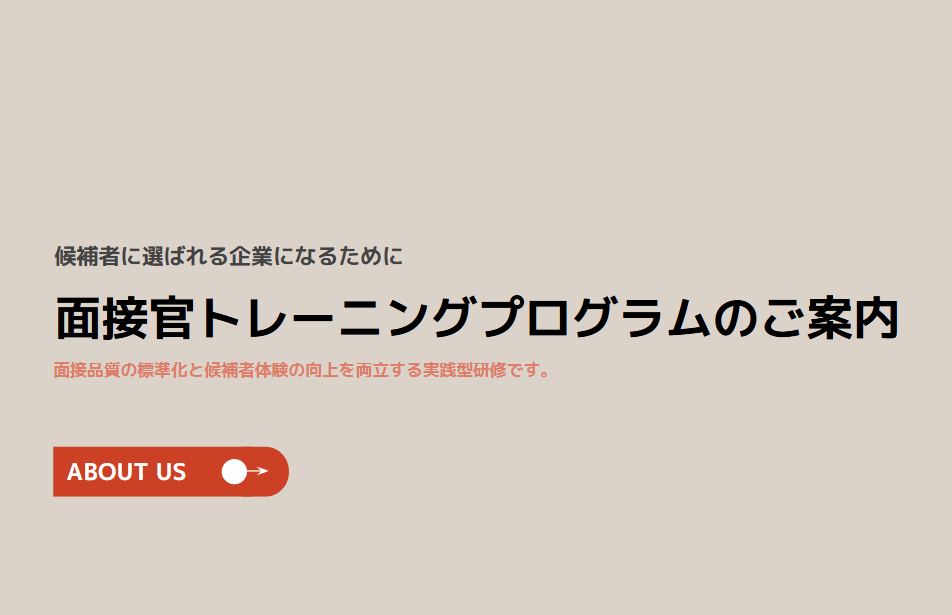
そもそもカジュアル面談とは
カジュアル面談とは、企業と候補者がお互いを理解することを目的に、リラックスした雰囲気で行う非選考型の面談です。
実施タイミングは選考前が一般的ですが、最近では内定後のフォローとして活用する企業も増えています。終始穏やかな空気で進めることで、候補者が本音を話しやすくなり、面接では見えにくい一面や価値観に触れることができます。
より自然な対話を促すために、私服での実施やカフェ・オンラインなどの環境づくりを工夫するケースもあります。担当者は人事だけでなく、現場社員や経営層が登場する場合もあり、柔軟な設計が可能です。
またカジュアル面談は、ダイレクトリクルーティング(スカウト採用)において、スカウトメールに続く次のステップとしても活用されます。
つまり、「まずは気軽に話してみませんか?」という、企業側からのナチュラルなアプローチとして機能する重要なフェーズです。
カジュアル面談の目的
カジュアル面談には、候補者との接点をより良いものにするための3つの明確な目的があります。
✔️ 相互理解によるミスマッチ防止
リラックスした雰囲気のなかで、
お互いの期待と現実のすり合わせを行い、ミスマッチを防ぎます。
✔️ 候補者との関係構築
ざっくばらんな対話を通じて信頼関係を築き、
志望度の向上や内定辞退の防止につなげます。
✔️ 自社の魅力を直接伝える
1対1での対話を通じて、
言葉や空気感で自社のカルチャーや価値観を届けられます。
カジュアル面談の基本についてより詳しく知りたい方は、こちらもご覧ください。
▶︎
【企業側】カジュアル面談とは?目的や面接との違いから流れまで解説
カジュアル面談でよくある逆質問|具体例と回答例
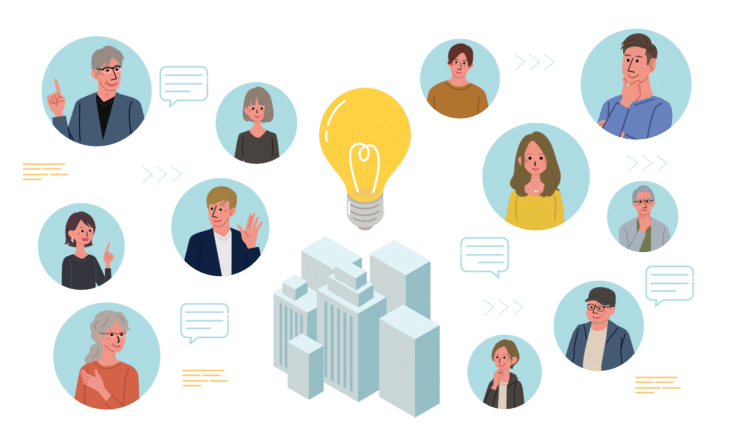
カジュアル面談の中で、候補者からよく出てくる「逆質問」。
ここでは、実際によくある質問の具体例と、その裏にある候補者の本音、そして好印象につながる企業側の回答例をセットで紹介します。
なお、企業側から候補者にどんな質問を投げかけるべきかを知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
▶︎
【企業側】カジュアル面談の質問集と伝えるべき内容|失敗例やコツも紹介
💬 よくある質問①:社内の雰囲気について教えてください
候補者の本音
- 厳しい上司がいたら合わないかも…
- ピリピリした雰囲気の中で働くのは不安
- 自分の性格に合った空気感なのかを確認したい
企業側の回答例
「一言でいうと風通しの良い職場です。
上司・部下の関係もフラットで、社員同士のコミュニケーションも活発ですね。
新しい提案も歓迎される文化です」
「穏やかなタイプの社員が多く、感情的になるような人はいません。
指導やフォローも丁寧なので、新しく入った方も安心して馴染めると思います」
💬 よくある質問②:御社のワークライフバランスについて教えてください
ワークライフバランスを重視する候補者は年々増えており、この質問は特に関心の高いテーマの一つです。
「残業時間の平均は?」「有給休暇は取りやすいですか?」といった、より具体的な聞き方をされるケースもあります。
候補者の本音
- いわゆる「ブラック企業」に該当しないかが気になる
- 前職のように残業過多にならないか心配(転職者の場合)
- 有給休暇を取得しやすい環境かを知りたい
企業側の回答例
「当社では従業員のワークライフバランスを重視しています。残業時間は平均で〇時間ほど、有給休暇の取得率は〇%です。
出産や子育て、介護などさまざまなライフステージに応じた働き方ができるよう、各種制度も整えています」
「以前は課題もありましたが、その経験を踏まえて現在具体的な改善を進行中です。
たとえば……(ここに実施中の制度や実例を紹介すると効果的です)」
💬 よくある質問③:理念は業務にどのように反映されていますか?
理念には企業が大切にしている価値観・信念・理想が込められており、候補者にとって共感しやすい項目のひとつです。
だからこそ、面談では「掲げている理念が現場で実際にどう活かされているか」を確認したいという声が多く寄せられます。
候補者の本音
- 理念に共感したが、実際に現場の判断や行動に落とし込まれているのか気になる
- 理念が本当に活きているなら、きっと風通しの良い組織だろうと思える
企業側の回答例
「当社の理念に関心を持ってくださりありがとうございます。
私たちは理念を“経営の軸”かつ“日々の判断基準”として重視しており、事業の方向性や社内文化にも反映しています。
たとえば…(ここに日常の実践例を加えると説得力が高まります)」
💬 よくある質問④:研修制度などスキルアップの機会はありますか?
自己成長の機会を重視する候補者が多く、「研修制度」や「スキルアップの支援」がどの程度整っているかはよく聞かれるテーマです。
候補者の本音
- 従業員の育成にどのくらい注力しているかを知りたい
- 成長意欲や学習意欲の高さを企業にアピールしたい
- 今の自分のスキルではやや不安があり、サポート体制を確認したい
企業側の回答例
「はい、教育制度も充実しています。入社時の新入社員研修をはじめ、3か月後のフォローアップ研修、
階層別のマネジメント研修など、各フェーズに応じたプログラムを用意しています。
また、希望者はeラーニングや通信教育も自由に受講可能です。制度ごとに必須/任意の区分も事前にお伝えしています」
💬 よくある質問⑤:どのような社内イベントがありますか?
社内イベントに関する質問は、社員同士のつながりや職場の雰囲気を知るためによく出るテーマです。
プライベートとのバランスを気にする人も多いため、柔らかい雰囲気で答えるのがおすすめです。
候補者の本音
- 社員同士の仲を深める機会はあるのか知りたい
- 仕事以外のコミュニケーションがあるのか確認したい
- プライベートの時間が必要以上に削られないか心配
企業側の回答例
「年間を通してさまざまなイベントがあります。
忘年会や新年会、社員旅行に加えて、最近ではバーベキューやボードゲーム大会なども実施しました。
昨年は〇〇に旅行へ行ったのですが、その話でいまも盛り上がることがありますね」
イベントの話の後に「〇〇さんは旅行はお好きですか?」といった雑談につなげるのも効果的です。
💬 よくある質問⑥:御社で活躍している方の特徴を教えてください
「自分もこの職場で活躍できるか?」は、候補者が最も気になるポイントのひとつ。
企業側にとっても、求める人物像やカルチャーフィットを伝えられるチャンスです。
候補者の本音
- 自分も同じように活躍できそうかを見極めたい
- 選考時にアピールすべきポイントを知っておきたい
- 活躍している社員に自分が似ているかを知りたい
企業側の回答例
「社内全体で見ると、自発性と行動力のある方が活躍しています。
指示を待つのではなく、課題を自ら発見し、主体的に提案・実行できるタイプの方が成果を上げやすいです」
「たとえば今回の募集ポジションで活躍している社員は、
顧客がまだ気づいていない課題を掘り起こし、即座に仮説を立てて提案するといった行動ができています」
「また、事業への共感やチーム志向も重要な要素です。
周囲と連携しながら成果を出せる人ほど、社内で長く活躍しています」
💬 よくある質問⑦:御社に内定する方の共通点を教えてください
候補者がこの質問を通して知りたいのは「内定に近づくためのヒント」。
選考の公平性を保ちつつ、傾向としての共通点を共有することは問題ありません。
候補者の本音
- 自分がその共通点に当てはまるかを確認し、内定の可能性を測りたい
- マッチ度の高い振る舞いや特徴を把握して、選考で意識したい
企業側の回答例
「成長意欲の高い方が多いですね。社員の育成に注力していることもあり、そういった点が自然とマッチするのだと思います」
「また、積極性のある方も多いです。
たとえば、グループディスカッションなどで発言をリードしたり、場面に応じて率先して動く姿勢が印象に残っています」
💬 よくある質問⑧:身に付けておくべきスキルはありますか?
志望度の高い候補者ほど、この質問を投げかけます。
「入社前から準備したい」という前向きな姿勢を評価しつつ、必要なスキルやサポート体制を伝えましょう。
候補者の本音
- 内定後に困らないよう、今から備えておきたい
- 志望度の高さをアピールしたい
企業側の回答例
「多くの社員が ITパスポート を取得しています。
社内外でITツールを使う場面が多く、基本的なリテラシーがあるとスムーズです。
ただし、資格取得については入社後にもサポート体制がありますので、今は意欲だけでも十分ですよ」
「また、今回のポジションでは TOEIC750点以上 を歓迎条件として設けています。
グローバル案件やクライアントとのやり取りがある場合には役立ちます」
💬 よくある質問⑨:入社後から配属までの流れを具体的に教えてください
入社直後は誰しも不安を感じやすいタイミング。
その不安を和らげるためにも「いつ」「どこで」「誰が」「何をするのか」をできる範囲で丁寧に伝えるのがポイントです。
候補者の本音
- 入社初日〜配属までの流れを把握して安心したい
- 放置されないか、歓迎される雰囲気があるか確認したい
- 現場が受け入れ準備できているかを感じ取りたい
企業側の回答例
「入社後はまず本社で約2週間の新入社員研修を実施しています。
ビジネスマナー、会社の理念や事業内容の理解などを中心に行い、その後は配属先でOJTがスタートします。
OJTは入社3年目の先輩社員が担当予定で、日々の業務を通じて実践的に学べる環境です」
💬 よくある質問⑩:具体的な業務内容について教えてください
候補者は「自分が入社後に何をやるのか」を具体的に知りたいと考えています。
ホームページや求人票に書ききれない“リアル”を丁寧に伝えましょう。
候補者の本音
- 実際にどんな仕事をするのか、イメージを具体化したい
- 希望とギャップがないか確認したい
- 自分が活躍できるかどうかを想像したい
企業側の回答例
「配属後は、既存のお客様への対応と、新規顧客の開拓を大体7:3の割合で行います。
既存顧客には定期的な打ち合わせを行い、必要に応じて追加提案も行います。
新規開拓については、テレアポやアポイント訪問を先輩と一緒に行う流れです」
💬 よくある質問⑪:今後の事業展開について教えてください
候補者は、企業の将来性に大きな関心を持っています。
「この会社に長く勤めても大丈夫か」「今後どう成長していくのか」は、入社を決めるうえで重要な判断軸になります。
候補者の本音
- 企業としての将来性があるかを見極めたい
- 成長分野やビジョンに自分が貢献できるか考えたい
企業側の回答例
「今後は〇〇分野への進出や、〇〇業界でのシェア拡大を計画しています。
また、新たなサービスの立ち上げや海外展開なども視野に入れており、組織としての成長をさらに加速させていく方針です。
(候補者名)さんにも、ぜひ〇〇分野で力を発揮していただけたらと考えています」
💬 よくある質問⑫:〇〇様が入社された経緯を教えてください
カジュアル面談では、企業全体ではなく「目の前にいる人」がどのように入社したかを聞かれることがあります。
面談担当者のリアルな視点を知ることで、候補者は企業へのイメージを具体化しやすくなります。
候補者の本音
- 個人の体験談を通じて、リアルな雰囲気を知りたい
- 自分と似たような視点・動機で入社した人がいるか知りたい
企業側の回答例
「私は2019年に中途で入社しました。それまでは同じ業界の別企業で働いており、業務には一定の満足感がありました。
ただ、自分のスキルや視野をもっと広げたいと感じていたタイミングで、今の会社を知り、
“成長機会の多さ”や“カルチャーの柔らかさ”に惹かれて入社を決めました」
💬 よくある質問⑬:募集の背景について教えてください
中途採用の場面では、募集の背景が候補者の関心を引きやすいポイントです。
不安を与えず、前向きな内容にフォーカスした説明が求められます。
候補者の本音
- 離職者が出た穴埋めではないか不安
- 組織に落ち着きがあるのかを確認したい
- 実際の理由と募集要項に食い違いがないかを見ている
企業側の回答例
「今回の募集は、チーム体制の強化が目的です。
新しいプロジェクトの立ち上げに伴い、追加で人員を確保する必要が出てきたため、ポジションを新設しました。
組織の成長フェーズで、役割や挑戦の幅が広がっているタイミングです」
カジュアル面談の逆質問に関する重要ポイント

カジュアル面談の逆質問に関する重要ポイントを、4つ紹介します。
正確かつ具体的に回答する
カジュアル面談では、候補者から「実際の働き方」や「チームの雰囲気」など、実務に踏み込んだ質問が投げかけられます。
その際、企業サイトや求人媒体に掲載されている情報と矛盾のない、正確で具体的な回答が求められます。
候補者の多くは、事前にインターネット上の情報をしっかり読み込んでおり、「言っていることがWebと違う」と感じると一気に不信感が生まれます。
だからこそ、面談担当者はあらかじめ自社の公開情報をチェックしておき、どこまでをどのように話すかの共通認識を持っておくことが大切です。
また、その場で答えにくい内容に対しては、無理に回答しようとせず、「確認して後ほどお伝えします」と伝えることで誠実さが伝わります。
その対応自体が、候補者にとっての信頼獲得につながります。
ネガティブな回答は改善の姿勢とあわせて示す
カジュアル面談では、候補者から残業時間・評価制度・職場の雰囲気など、やや答えづらい質問が投げかけられることもあります。
そうしたときに大切なのは、事実を正直に伝えつつ、改善に向けた取り組みをセットで話すことです。
たとえば、残業時間が業界平均よりやや多めである場合、嘘の数値を言ったり、ごまかしたりするのは逆効果。
「以前は平均〇時間でしたが、現在は〇時間まで短縮できています。社内では業務フロー見直しやシステム導入なども進めています」など、改善のプロセスを具体的に伝えることで、信頼を得ることができます。
あくまで候補者が知りたいのは「課題の有無」ではなく、「その課題に企業がどう向き合っているか」。
正直さと変化への前向きな姿勢こそが、企業文化や風土への信頼感につながります。
事前にネットなどで自社の評判を把握しておく
カジュアル面談に臨む候補者の多くは、企業HPだけでなく、SNSや就活・転職口コミサイトなどを通じて、事前に企業の評判を徹底的にリサーチしています。
なかには、事実と異なる情報や、極端な個人の意見がそのまま掲載されているケースも珍しくありません。
そうした情報に初めて触れた候補者にとって、その内容が正しいかどうかを判断するのは難しいもの。
だからこそ、企業側が「候補者の先入観」を事前に把握しておくことが、面談の満足度を大きく左右します。
面談前に「企業名+評判」「企業名+口コミ」などで検索し、誤解を招きそうな点や、補足が必要なテーマを洗い出しておくのがおすすめです。
意図せず候補者が不安を感じてしまう場面を減らすことで、より前向きな対話が生まれます。
よくある逆質問の回答例を準備しておく
カジュアル面談における逆質問は、候補者の志望度や企業理解度に大きく関わる重要な場面です。
本記事で紹介したようなよくある逆質問パターンに対する自社版の回答例を、あらかじめ整理しておくことで、面談の質を大きく高めることができます。
特に「残業時間」「社風」「活躍人材」など、ネガティブ要素を含む可能性があるトピックについては、
回答に一貫性を持たせることで、企業全体としての信頼感にもつながります。
- スムーズな質疑応答が可能になり、面談が自然な流れで進む
- ネガティブな話題にも、ポジティブな印象を残したまま対応できる
- 面談担当者ごとの回答にばらつきが出ず、候補者に安心感を与えられる
- 自社サイトや求人票の情報と矛盾がなくなり、企業理解が深まりやすい
- 選考過程全体で、一貫したメッセージを届けることができる
逆質問に備えたテンプレートを社内で共有し、面談担当者ごとの“属人化”を防ぐことで、候補者からの信頼をさらに高めることができます。
まとめ
本記事では、カジュアル面談で頻出する逆質問について、候補者の本音や企業側の回答例をセットでご紹介しました。
いずれも実際の面談現場でよく問われる内容です。「自社の場合はどう答えるか?」を、あらかじめ考えておくことで、面談の質と信頼性は大きく向上します。
また、逆質問だけでなく「企業側からすべき質問」についても整理しておくと、面談は一方通行ではなく、相互理解の場としてより有意義なものになります。
以下の記事もあわせてご覧ください:
▶︎
【企業側】カジュアル面談の質問集と伝えるべき内容|失敗例やコツも紹介
なお、ダイレクトソーシング社では、過去70万件以上のデータと40媒体以上の知見を活かし、
貴社に最適なダイレクトリクルーティングの戦略設計・候補者対応・面談設計をサポートしております。
自社に合った面談の型や、ターゲットに応じた逆質問対策を相談したい方は、
以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください(無料)。
面接の属人化・評価のバラつきといった悩みを解消するための、実践的なトレーニングプログラムをご紹介しています。
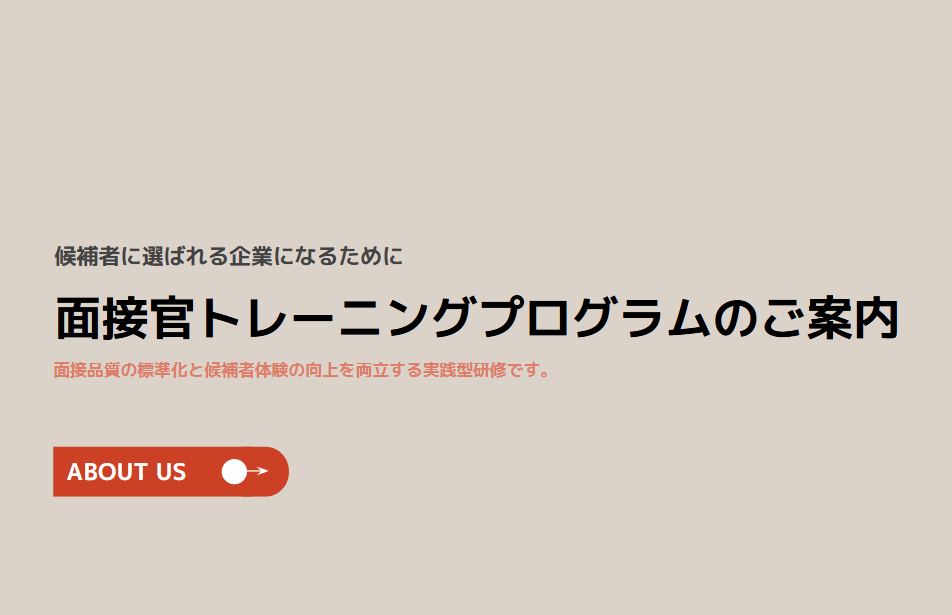

45分の気軽な相談会を
開催しています

竹村 朋晃
著者プロフィール 竹村 朋晃(Tomoaki Takemura)
株式会社ダイレクトソーシング 代表取締役CEO
▶︎ LinkedInプロフィールを見る
2005年に野村総合研究所に入社。大手損害保険会社のシステム設計・開発に従事し、エンジニアとしてのキャリアをスタート。 2015年、ダイレクトソーシングの可能性に着目し、株式会社ダイレクトソーシングを創業。データドリブンな採用を軸に、候補者データの構造化、スカウト改善、タレントプール構築などを通じて、累計500社以上の採用支援を行う。 2017年よりLinkedIn公式パートナーとして、日本企業へのLinkedIn活用を支援。2025年には「LinkedIn Student Career Week」を主催し、5,000名超の学生と40社超の企業をマッチングさせるなど、イベントプロデュースでも実績多数。 「Stand Alone Complex Society(個が独立し共創する社会)」の実現を掲げ、採用における価値創造を追求している。 趣味はウェイクボードとテニス。お台場在住。技術と営業を横断する“ハイブリッド人材”として、採用の進化に挑み続けている。

